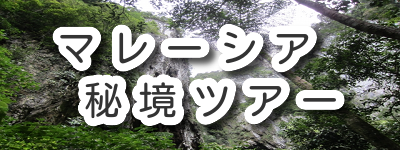どこまで必要?ムスリムの為のハラル対応<SDGs 目標 4・10・17>
![]()
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。
![]()
2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。
![]()
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。
【参考資料】
国際連合広報センター
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/31737/
マレーシアの国教は「イスラム教」
世界の総人口の4分の1人がイスラム教徒で、世界最大の宗教といわれているキリスト教徒の人口を抜き、イスラム教徒人口が世界一になるとも言われております。
日本で暮らしているとあまりか関わることがない宗教なので、ハラルの定義とは何?日本食は作れるの?とおもてなしの心はあるのだけど、不透明なところが多いですよね。実はハラルとは食に関するものだけと思われがちですが、イスラムの教えで「許されている」(合法なもの)という意味で、神に従って生きるイスラム教徒の生活全般に関わる考え方なのです。
マレーシアの国教は「イスラム教」で、人口の約69%がマレー系と言われているイスラム教徒なので、身近にハラルを感じることができます。




参考URL: https://www.atglobal.co.jp/strate/263
マレーシア国内でのハラル
マレーシアで生活しているとイスラム教徒が多いこともあり、レストランやスーパーマーケット等どこに行っても、ハラル認証マークを見ることができ、ハラルが日常生活に溶け込んでいるので、さほど気にならないのが現状です。
ノンハラル(ハラルでない=豚肉・酒など)は手に入りにくいのかというと、そうではありません。スーパーマーケットには【ノンハラル】商品のみを陳列している場所があり、そこで支払いを済ませれるシステムになっています。その場所には「Non Halal」と看板が上がっていますので、イスラム教徒にも一目でわかるようになっています。

マレー料理の屋台ではハラルマークの付いた看板を見かけることはほとんどありませんが、スタッフがイスラム教徒であれば調味料にしても食品にしても、ハラルのものを使っているであろうということで、ハラルかどうかを確認することはほとんどありません。ですが同じマレー料理の屋台でも、イスラム教徒ではないスタッフが販売していると、他の屋台にすることもあります。
プログラム実施方法一例 【クアラルンプール】
食の【ハラル対応】について学ぶ
ハラル認証キッチンを持つイスタナホテルのシェフにより認証を受けるためにはどのような対応が必要かなどの講義があります。 ハラル認証機関というものは世界共通というものはなく、各国で授けれた条件をもとにハラル認証がされており、マレーシアには国が管轄しているハラル認証機関(マレーシア・イスラム開発局(Jabatan Kemajuan Islam Malaysia:JAKIM)があり、 ハラル認証は条件が厳しいことで有名で他国からの信頼度も高く、日本でもパートナーシップ契約をされている機関もあります。

キッチンバックヤード
キッチンにはハラル認証を受けた箇所をそうでない箇所が同じフロアーにあり、実際にどのように分けているのかを見学致します。
市場調査
ハラル認証を受けている商品にはハラルマークが印刷されていて、イスラム教徒はハラル認証マークの有無を確認し購入しています。 スーパーマーケットでは、ハラル認証を受けていない商品も取り扱いがありますので陳列方法や、最近はハラル認証を受けたお好みソースや日本企業のハラル商品も多く売られていますのでそういった商品を日本と見比べていただけます。


ハラルとは決して難しいことではありません。イスラム教徒へのちょっとした心遣いです。食の【ハラル対応】を理解をすることにより、イスラム教徒が安心して食事ができ、お互いが楽しめるようになるではないでしょうか 。
オンラインで学ぶキャリアアップとSDGs ILKAプログラム
日頃の生活では得ることの出来ない、海外経験による多様性あるマインドやスキルを身につける為のオンライン教育サービスです。「インプット」だけでなく、成果物が求められる環境で「アウトプット」するまでをゴールとする、自発性に特化したプログラムです。